

| パナデリアでもずっと勉強をしているチョコレート。 今回は、会員の皆さんと一緒に『 明治製菓 坂戸工場 』にお邪魔しました。 | |
|
埼玉県坂戸にある明治製菓の関東工場、敷地面積はなんと約3万坪!広い! 東京ドームの2倍以上もあるんです。 この中に、工場や配送センター、研究所などの施設が集まり、関東地区のお菓子の供給をコントロールしています。 工場長の石塚さんに案内していただき、見学スタートです。厳重な装備に身を包んでいざ工場へ! それでは チョコレートができるまでをご紹介します。 | 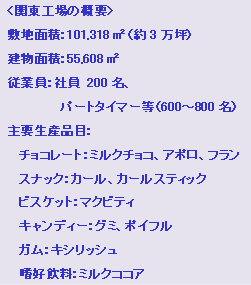 |
|
広い工場内ですが作業をする人はまばら。完全にオートメーション化されているので、機械の調整や、目視、手作業などが必要な場所でのみ人間による作業が行われています。 人間が入る場合は、まず左右から強い風が吹き出てくる狭いスペースに入り1回転して衣服についた埃など汚れを取り除きます。そして粘着テープで白衣の汚れを取り、手を除菌するという徹底した衛生管理が行われています。 |
 白衣 |
1. 原料となるカカオ豆が工場に到着します。
明治製菓のカカオ豆は、1年中品質の安定しているガーナの豆がベースになっています。1年で加工する豆の量は約1万トンだそうです!2. 選別(クリーナー)
悪い豆や砂、金属、小さい石などのゴミを取り除き、良い豆だけを残します。さらに高温の蒸気で殺菌します。3. 分離(ウィノワ)
豆を砕き、皮を吸引して取り除きます。こうしてできたものをカカオ・ニブと言います。4. 焙焼(ロースター)
カカオ・ニブを炒って、カカオ豆独特の香りを引き出します。この段階では『苦味』『酸味』がかなり強い状態です。5. 配合(ブレンダー)
チョコレートの風味をよくするため、数種類のカカオニブをブレンドします。
工場内はチョコレートの甘い匂いが立ち込めてむせかえるよう!しかもとっても暑いんですよ。 6. 磨砕(グラインダー)
約80℃でカカオ・ニブをすり潰します。カカオニブには脂肪分(ココアバター)が55%も含まれているので、すり潰すとドロドロの状態のカカオマスになります。7. 混合(ミキサー)
一部は搾油の工程を経て、カカオバターとココアになります。 ドロドロのカカオマスに、ミルクや砂糖、ココアバターなどを混ぜ合わせ味を調えます。8. 微粒化(レファイナー)
ローラーにかけて、舌の先でもざらつきを感じないほどに、なめらかにします。 始めはザラザラとした粒子を感じますが、何段階にも分けて粒子を細かくすることにより、滑らかな舌触りのチョコレートが完成します。9. 精錬(コンチェ)
コンチェという機械で、長時間かけてよく練り上げます。1回に練り上げる量は4トン。中ではスクリューが回転し、揮発性の成分を飛ばします。ここでチョコレートがさらになめらかな状態になります。10. 調温(テンパリングマシン)
チョコレートの温度を調節して、含まれているココアバターを安定した結晶にします。 テンパリングをすることで、ツヤが生まれ、チョコレートがきれいに固まるようになります。ここからはベルトコンベアが中心の涼しそうな工場での工程です。
次々に板チョコが出来上がり、箱詰めされる様子を見学しました。11. 充填(モールダー)
型に流し込み、振動を与えてならし、気泡を取り除きます。12. 冷却(クーリングトンネル)
冷却コンベアにのせて冷やして固めます。トンネルを通る間に約30℃のチョコレートが5〜10℃に冷却され、しっかり固まって出てきます。13. 型抜(デモールダー)
型をハンマーでたたき、ひねってチョコレートをはがします。14. 検査
人間の目で、形や色ツヤなどおかしいところがないかしっかり確認します。15. 包装(ラッピングマシーン)
アルミ箔やレーベルでチョコレートを包装し、最後にダンボールケースに詰めます。16. 熟成(定温倉庫)
チョコレートの品質を安定させるため、温湿度を調整した倉庫の中で一定期間熟成させます。
|
工場見学を終えチョコレートについてすっかり詳しくなった私達ですが、チョコレートの魅力はまだまだ計り知れません。 チョコレートで博士号を取ったという明治製菓のチョコ博士 古谷野 哲夫 さんに、"おいしいチョコレートの秘密"などカカオについてさらに詳しいお話を伺いました。 |
| →つづく |