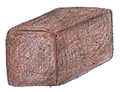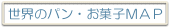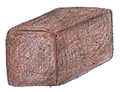 プンパニケル
プンパニケル |
 ブレッツエル
ブレッツエル |
 シュトーレン
シュトーレン |
 ツッカーブロート
ツッカーブロート |
 バームクーヘン
バームクーヘン |
 シュヴァルツヴェルダー・キルシュトルテ
シュヴァルツヴェルダー・キルシュトルテ |
 ヒンベールトルテ
ヒンベールトルテ |
 アプフェルトルテ
アプフェルトルテ |