
|
「ここはまるでフランス菓子の博物館のようだ!」 フランス人がそんなふうに驚くほど、「オーボンヴュータン」には様々なお菓子が溢れている。ケーキや焼菓子はもちろん、見たことのないコンフィズリーやヴィエノワズリ、そしてコンフィチュールなどなど。その中でも、お菓子好きを一番ワクワクとした気持にさせてくれるのは、素朴で美しい地方菓子や伝統菓子ではないだろうか。見た目は素朴だけれど、その深い焼色や独特の形に、なぜか心が惹きつけられる。 そこで今回は、フランス人以上に“フランスの伝統菓子”を愛し、日本で伝え続けている、河田勝彦シェフにお話を伺った。 |
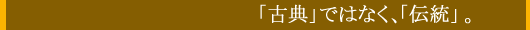 |
||||
|
「まず言いたいのは、“伝統”と“古典”では、まったく意味が違うということ。お菓子で言う“古典”や“クラシック”というのは、現在のお菓子の基礎となっている“エスコフィエの時代”を指す事が多いですね」 ちょっと難しく聞こえるが、“エスコフィエの時代”のケーキとは、バタークリームなどを使った重たいスタイルのこと。河田氏によれば、古典=“エスコフィエの時代”と括れる一方で、伝統菓子のスタイルは形がなく、もっと曖昧ないものだという。 「例えば、フルーツ。フレッシュもおいしいけれど、1週間、1ヶ月・・・、いっそ1年間ずっと食べていたいという欲が出てくる。そこから生まれたのがセック、ドゥミセック、コンポート、ミ・コンフィ、コンフィです。また、その土地によって、オレンジだったり、サクランボだったりと、とれるものが違います」 当然ながら産地では、これらの加工品を使ったお菓子が生まれる。これが、伝統菓子というわけだ。 |
|||
|
|
「必然的に生まれた伝統菓子は、実際には粗野なものも多いですし、その土地によって組合せるフルーツやナッツなどが変わることもある。それから、ヨーロッパは陸続きなので、文化の流れも影響してきます。例えば、“クラフティ”が、ブルターニュ地方で“ファーブルトン”になるというように。自然発生的に生まれ、伝わり、広まる。これが伝統菓子です」
ひとつのお菓子の背景に、歴史や文化、人々の思いが見えてくる。伝統菓子のおもしろさが、ここにある。 「菓子は、あくまでおいしくて楽しいもの。でも、それだけじゃ僕は嫌なんです。背景となっているものを求めていきたい。文化や気候といったものが、どんなふうにひとつのお菓子を生み出したのかを知りたいと思っているんです」 |
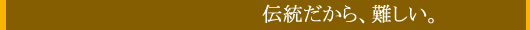 |
||||
|
だが、その伝統菓子が危機的な状況にある。例えば、 “ミルリトン”。日本では比較的ポピュラーな伝統菓子だが、なんとパリはおろか、発祥の地ルーアンのパティスリーでも、まったくお目にかかれなくなっているのだ。少しずつ姿を消しつつある伝統菓子。今となっては、人づてに調べることも難しく、文献が頼りになっている。
「ひとつのお菓子でも、本によって伝え方が違って、どれが本当なのかわからない部分がある。だから、まずは文献通りに作ってみます。実際、すごくいいというものもあれば、これはヒドイ、この配合はありえないというものもある。なかなか、難しいですよ」 そう話す姿は、まるでお菓子の歴史家だ。実際、河田氏はパティシエの仕事を終えると、歴史家に早がわりする。フランス全土の伝統菓子を集大成として1冊の文献にまとめるべく、毎日のように書斎にこもる日々を過ごしているのだ。もちろん現地の情報も必要と、渡仏中の息子にフランス中を周らせ、資料集めに奔走する。すべては、フランス伝統菓子を残し、伝えるため。いったい、この情熱はどこから生まれるのだろうか。 |
|||
 |
||||
|
そもそも、河田氏が菓子修業のため、ひとりフランスへと渡ったのは今から約45年前。1967年、東京オリンピックや安保闘争の年だ。 「当時は、フランス料理店といっても宮内庁などひと握りのVIPだけのものでした。それでも、レベルはかなり低かったですね。僕はパティシエとして米津風月堂で働いていましたが、アーモンドなんてみたこともありませんでした。フルーツも、缶詰めのパインや桃。バターはありましたが、フランスのマーガリンよりもひどいというような代物でした」 フランスで本場のケーキを学びたい。熱い想いを胸に、河田氏は日本を飛び出した。 「フランスで食べたお菓子は、本当においしくて仕方なかった。お酒と砂糖がしっかり効いていて。こんなにおいしいものがあるのかと思いました」 待っていたのは、本場の圧倒的なおいしさ。河田氏は、初めて知るおいしさに夢見心地になっていた。 |
|||
|
「ところが、フランス人と同じ体質にできていないせいか、フランスで1、2年過ごす内に、しつこく感じるようになってきたんです。こんなにおいしいのに飽きてしまうということが、自分でもショックでした。そこで理由を考えてみたんです。例えば、クレームはおいしいけれど、非常に濃厚。それが、ビスキュイの間に2cmも挟んであるから、どうしても重たく感じてしまう。これは、あくまで作り手の問題で、構成の仕方に問題があるんじゃないかと思うようになったんです」 味覚は幼少期で決まるという。いくらパティシエといっても、日本人である河田氏の舌にはどこかに違和感が残った。 「そんなこともあって、何年か経つうちにお菓子がいやになりかけた。でも、この国には、まだ何かあるだろうという気持が捨てきれず、1年間地方に出ることにしたんです。 そこで河田氏が初めて出会ったのが、“カヌレ”や“ファーブルトン”といったお菓子。パリでは見たこともない地味なお菓子だったが、味にも姿にも心惹かれるものがあった。なぜ、みんなはこのお菓子をやらないのだろう、と思ったという。 「そこで、パリに戻って職場で話したのですが、誰もそんな地方の地味お菓子のことは知らなかった。当時のパリは、封建的ななかに、冒険心に富んだお菓子が登場し始めた頃。だれも地方の伝統菓子には目を向けなかったのです」 古典から現代へと、まさにパティスリーの時代は移りつつあった。だが、素朴で垢抜けない地方のお菓子は、その圏外に取り残されてしまっていたのだ。 |
 |
||||
|
1975年に帰国した河田氏は、1981年「オーボンヴュータン」をオープンした。ショップを埋め尽くすのは、河田氏がそのおいしさに感動した本格的なフランス菓子。だが、たちまち人気に・・・と言うわけには行かなかったそうだ。 「最初の10年間は大変でした。そのためにやり方を変えた人もたくさんいます。でも、僕には変えられなかった。大体、日本のスポンジの作り方を知らないんですから。でも、少しずつファンはついてきてくれたということです」 背景となる食文化や歴史が異なる日本とフランスでは、好まれる味が違うのは当然のこと。だが、それを知った上で、あえて河田氏は何ひとつ変えず、ひたすらフランスと同じ味を作り続けた。そこに葛藤はなかったのだろうか。 「僕は不器用な人間なんです。何とかものにしてやろう、そう思っただけ」 と照れくさそうに語る。作りたいのは、フランスで自分が感動し虜になった味。みんながどう思うか、受け入れられるかどうかは関係なかった。 「僕は、儲かるとか、儲からないとか、そういう商業的な考え方が大嫌いなんです。本当は(商売にとって)良くないことなんでしょうけど、売れる、売れないという判断基準で決めるのが嫌いで・・・」 ちょっと矛盾するようにも聞こえるが、河田氏は売るためにケーキを作っているわけでないのだ。自分が作りたいから作る、だから当然そこに、妥協や甘えはない。その頑ななまでのこだわりは、今は失われつつある職人の姿なのかもしれない。 |
|||
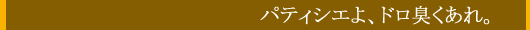 |
|||||
|
「菓子屋なんてもっとドロ臭くていいんです。それから、フランス菓子だけでなく、もっと食や菓子の世界を知らないとダメ。料理人と違って、意外に知識や経験が少ない人が多いと思います」 職人気質の菓子屋、河田氏だからこそ、最近のパティスリー界に対して、思うところは色々とあるようだ。
「シェフは先頭に立って戦わなきゃいけないと思います。フランスで修業していた頃、シェフは必ず他のスタッフより2時間は早く着いて仕事をしていた。とにかく、シェフは人一倍働いていましたね。そういう姿は見習うべきだと思いますよ」
そんな想いから、河田氏も先頭に立ってスタッフを守り、できる限り厨房にいるようにしているそうだ。それに、店(販売スペース)はなんだか恥ずかしくてね、と言い訳を添える。 「それから、自分にとってプラスになったことは、他の人にも与えるようにすればいい。例えば、フランスに行かせてもらったこと、自由な時間を作ってもらったこと。自分が楽しかったことは、後輩たちに、ぜひ体験させてあげてほしいですね」 |
||||
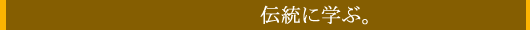 |
||||||
|
「フランスは今、冷却期だと思います。だからこそ、もっとしっかりやれよ、と言いたい。確かに、フランスは就労条件の関係で作業の効率化が求められています。かつて一緒に働いたことのあるフランス人の某有名シェフ達も、“やっぱり時代だから”と言って簡単な技術や製法に頼る人が多いです。確かに週35時間労働の枠内での仕事は大変だけれど、その中で何ができるかを考えれば無理ではないと思う。昔、僕がいた時代は5時には終わっていたんですから」 河田氏がフランスで修業していた頃は、どのパティスリーの厨房にも50年近くずっと働いているような熟達した職人がいて、いい意味での頑固さでおいしさを守っていたそうだ。時代は変わり、嗜好も移る・・・。だが、時代は変わっても、おいしさの芯の部分は変わらないはずだと、河田氏は信じている。 「一度いだいた志は、最後まで通しましょうと言いたい。それが、“伝統”という純粋な気持につながっていると私は思っているんです」 フランス菓子のおいしさに感動し、多くの人に伝えたいと思った河田氏の志は変わらない。時代に流されることなく、しっかりと人々の心に息づいてきた伝統菓子。それは河田氏の菓子屋としての生き様とも重なった。 (2011.1)

|
|||||
オーボンヴュータン
|
|
| 住所: | 東京都世田谷区等々力2−1−14 |
| Tel: | 03-3703-8428 |
| Fax: | 03-3703-0261 |
| 営業時間: | 9:00〜18:30 |
| 定休日: |
水曜日
|
| アクセス: |
東急大井町線尾山台駅徒歩5分
|
 |
Panaderia TOPへ戻る |









