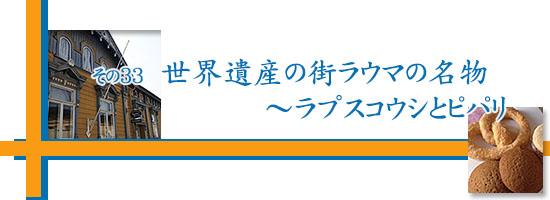
私がラウマを訪ねようと思ったのも、そんなツーリスティックな場所を歩きたかったから。日本も同じですが、木造であるがために火事や耐久性、戦争などの理由で古い佇まいは消滅している町が多いのです。フィンランドで3番目に古い町ラウマも、1682年の大火によって当初の街並みは消えたものの、18世紀から19世にかけて再建され、今日では現存する北欧最大の木造建築の街として人々の心を魅了し続けています。身近に例えるなら木曽路の馬籠や妻籠を歩くような気分かもしれませんね。 |
|
|
|
|
|
|
早速お料理から紹介しましょう。 料理名はラプスコウシ(Lapskoussi)。言いにくいけれどリズムある発音。それにツーリストインフォメーションの女性の説明ですぐに頭に入ってしまいました。彼女曰く「見た目は悪いけれど味はいいの。じゃがいもとお肉でぐちゃぐちゃだけど、とにかく味はいいの」、こう何度も唱えながら画像を開き、食べられるお店を案内してくれたからです。 時計の針は13時過ぎ、急ぎ足でそのレストランANKKURI THEATRE RESTAURANTに向かいました。入ってすぐにラプスコウシをオーダーすると、店員さんは微笑みながらトレーを差し出しご自由にとってくださいと…。そうでした! フィンランドではランチは大概ビュッフェ形式。カフェ同様、席を確保したら、先にレジで会計を済ませてトレーとお皿を取り、好きなものを食べられるだけ盛り付けるスタイルなのです。はやる心を抑えつつ、またもや店員さんをつかまえて、ラプスコウシはどれ?と尋ねます。 すると彼はLapskoussiというシールの貼ってある壺型の大きな鍋を指し、盛り付け方と食べ方を教えてくれました。壺の中のどろっとしたシチューのような、ゆるくて茶色いマッシュポテトのような煮込みを、お皿に丸く盛り付けたら中心に窪みを作り、そこに澄ましバターを垂らします。ビーツやピクルスを添えたらできあがり。バターを混ぜながら食べるのだそう。なんと素朴でボリューミーな料理だこと! 澄ましバターの泉にドキッとしながら、教わった通りに頂いてみました。これは…まるで2日目のシチュー、そして肉じゃがを彷彿させます。世界にはいろんな肉じゃががあるものです。肉の旨みをじゃがいもや根菜が吸って、野菜の甘さでまろやかになる。きっとこのコンビネーションは世界共通のうま味の壺。どこかで食べたような懐かしい味わいは、これがラウマの肉じゃがだからでしょう。 「見た目は悪いけれど味はいいの」 彼女のせりふが、再び浮かびます。 |
 |
| ラプスコウシをビュッフェスタイルで盛り付け。ビーツやきゅうりのピクルスを添えるのがお決まり。じゃがいもパンや糖蜜入りの黒パン、チーズも美味。 |
 |
| おかわりは、教えてもらった通り泉を作り澄ましバターを注いで…郷土料理をいただくときはカロリーのことは忘れるべし。 |
|
帰りがけに、あの店員さんが一枚の栞をプリントアウトしてくれました。 「THE STORY OF LAPSKOUSSI IN BRIEF」 英語で書かれたそれには、もともとラプスコウシは船乗りの持ち込んだ料理で、似た名前が多くのヨーロッパの港町にある。例えばドイツのLabskaus、スウェーデンのLapskojs、英国のLobscouseなど、いずれもその昔、海運業で繁栄した町の名物である。 ちょっと検索してみると、本当だ! 似たようなごちゃまぜ料理の写真が並んでいます。航海中には保存のきく塩漬け肉や根菜でしのぐしかなかった工夫から生まれたのでしょうか。肉じゃがのうま味を知った船乗りたちの語り継ぎが聞こえてきそうです。ラウマでは普段の食事や、特別な日の食事にラプスコウシが登場するとか。レシピはこれといった決まりはなく、その家によって様々。主な材料は牛肉、豚肉、根菜類で、あとは塩、コショウの味付けだけ。一番大切なのは長時間かけて煮込むこと。あの深いうま味は、時間という隠し味が醸すものだったのです。 |
 |
| ラプスコウシの入った鍋を前に、食べ方を丁寧に説明してくれたレストランのサーヴィススタッフ。 |
 |
| ANKKURI THEATRE RESTAURANT前の運河でも、教会と同じようなだまし蝋人形が泳ぐ! ラウマの町は茶目っ気たっぷりだ。 |
|
次はお菓子。教えていただいたカフェ・コンティオ(Café Kontio)に向かいました。旧市街の目抜き通りに、ブレッツェルの看板と黒いクマのロゴマークを見つけたらそこがお店。ショーウインドウには、人気のヴァニラムンッキとラウマンピパリという焼き菓子がディスプレイ―されていました。
ムンッキはフィンランド風のイースト発酵ドーナッツのこと。フィンランド人はムンッキが大好きで、パン屋さんやカフェには必ずといっていいほどあります。コンティオのショーケースにも様々なムンッキが並んでいました。ところが肝心のヴァニラムンッキはすでに売り切れで姿なし! さすが看板商品です。 |
 |
| Café Kontioの外観。Kontioの意味はクマ。 |
 |
| 看板商品はヴァニラムンッキですよ! |
 |
| ショーケースにはおなじみプッラ類の他、ポルトガル風、オランダ風、リング状…数種類のムンッキが並ぶがヴァニラは…売り切れ!? |
食べてみるとドイツのレープクーヘンのようなソフトな口当たり。そしてシナモンやクローブの香りが口いっぱいに広がります。こっくりとした甘さは北欧らしく糖蜜を使っているからでしょうか。フィンランドでピパリといえば、薄くパリッと焼いたタイプしか食べたことがなかったのでちょっとびっくり、新たなタイプとの出会いにうれしくなりました。 考えてみればここは港町。遠い南の国からスパイスが運ばれ、レープクーへンに似たものが伝えられたのかもしれません。スパイス菓子から世界のつながりを辿るのも面白いものです。 |
 |
| クラシックなショーウインドウに飾られた素朴なお菓子達。その中に雰囲気漂うラウマンピパリを発見。 |
 |
| お店の裏はカフェのテラス席。 |
 |
| グラニュー糖を塗した軽いパイのようなブレッツェル、ポルボロンのように脆い食感が印象的なジャムサンドビスケット。そしてマカロンのようにころんとかわいいラウマンピパリ。箱に記された材料は小麦粉、砂糖、卵、バター、シロップ、重曹、シナモン、クローブ。 |
|
それから、せっかくなのでショーケースでこちらを見つめる、Siilileivos〜ハリネズミケーキをいただくことに。 中身は見ただけで見当がつきました。昔ケーキ屋さんのショーケース片隅にあったポムドテールと同じ、ケーキクラムをラム酒漬けドライフルーツと混ぜて形作ったリサイクル菓子。遠いフィンランドの世界遺産の街で見たらなんだか懐かしくて…。 カフェ・コンティオのハリネズミケーキはミックスベリージャムでまとめてあり、チョコスプレーとチョコレートでコーティング。食べた感じはかなりヘビー、だけれど味は悪くはなかったです。 ラプスコウシにラウマンピパリ、ハリネズミケーキと、パステルカラーの木造家屋、ラウマの日帰り旅は、自分の中のノスタルジックな味覚の記憶を思い出させてくれました。 |
 |
| 素朴で伝統的なフィンランドの生ケーキ。日本と違いいちごは夏の定番。ラウマの伝統工芸であるレースにちなんだ「レースのケーキ」も気になるが…。 |
 |
| 目があってしまったハリネズミケーキを食べてみる。 |
 |
| 17世紀に伝えられたというラウマのボビンレースは、その質の高さで、ヨーロッパの貴婦人にもてはやされたそうだ。旧市庁舎1階にはレース博物館があり、町中ではレースショップをみかける。男たちが航海中、女たちはレース編みに勤しんでいたのだろうか…。 |
|
★ ラウマについて http://www.visitfinland.com/ja/kiji/utsukushi-ki-machi-rauma/ ★ ANKKURI THEATRE RESTAURANTサイト http://www.frescoravintolat.fi/?sivut/ankkuri.html ★ Café Kontioサイト http://www.kontion.fi/ |









